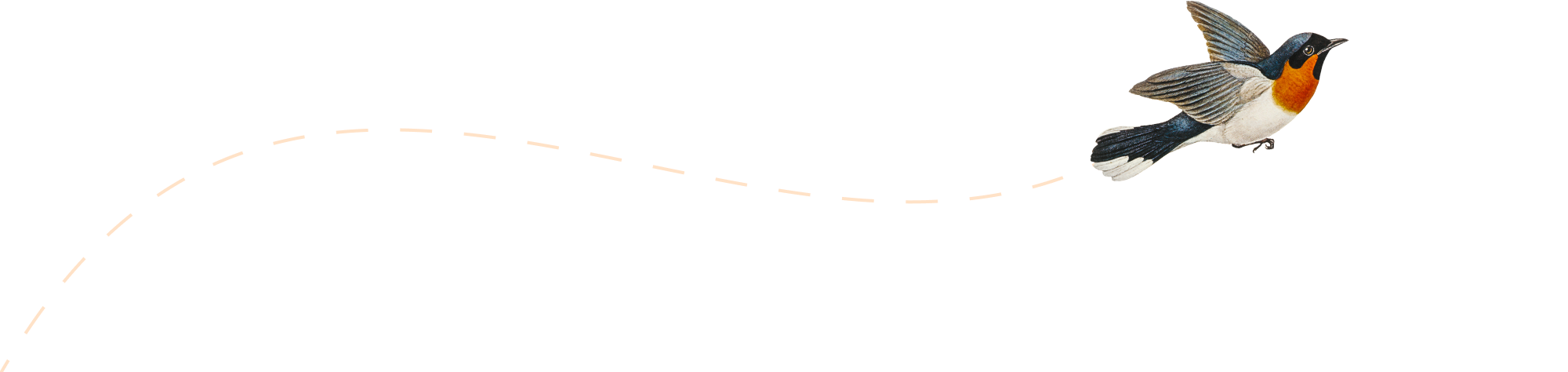-
粉もののアレルギーに関して
お客さんからの問い合わせは食に関することや農に関することなどで多岐にわたる そこで、それらに全力で返答しているので、せっかくなのでここで記録しておこうと思う 問い合わせ内容:娘が、ハウスダストのアレルギーがあり、常温保存 […]
-
食料難に備えて
お客さんからの問い合わせがあったのでブログにも記載しておく 「玄米の保存期間について教えてください。 これから食糧難の時代に突入されるとも言われております。備蓄を考えているんですが一般的に常温での保存は玄米だとどれくらい […]
-
12年目の作を終えて
稲刈りが終わった11月中旬、お客様からお菓子が届いた。 開けてみると一筆箋で、諸事情により終わらせていただきたい、との言葉が。 この方は自分が収納して最初のお米の販売の時からのお客様で、もう何度配達に伺ったかわからない。 […]
-
ネガティブ思考というか悲観的というか
自分は基本的にそういったものの見方をする。 小さいときはよく周りからどう見られるか、見られているかを気にして学校生活を送っていたように思う。 中学・高校とカッコつけてるつもりで周りの目を気にし、本当は何がしたいのか、どう […]
-
親孝行
自分はいくつかのメルマガやライン@を登録していて、毎日いくつかのメールなんかが届く。 大抵の場合は読む暇がないから題名も見ずにアーカイブしてしまうんだけど、冒頭の文章を少し読んで、面白そうだったら最後まで読んだりしている […]
-
足元を固める
2018年が始まった。32歳の1年。 稲作11年目、無農薬では10年目。50歳で引退するならあと18年だから、29年中の11年目。 あと18回しか稲作はできない。意外と少ない。 50歳で引退と書いたのは実際に稲作の舵取り […]
-
SLやまぐち
今年も1年があっという間に過ぎた。 ブログも書けなかったというより書かなかったのは子供との夜の時間を大事にしようと思ったから。 今日、12月23日は年内の仕事をおおよそ終わらせて、夏ごろから楽しみにしていた家族旅行中。 […]
-
新年
1年の計は元旦にあり、というのは脈々と続く日々にどこかで区切りをつけないと気がすまないからなのだろうか。 冬から春になるときが1年のはじまりという感覚は、人類が狩猟をしていた時から、つまり太陽暦などが産まれる前からなんと […]
-
新米の刈り取りが始まった
8月下旬から稲刈り前にやっておかなければいけない仕事をなんとか間に合わせ、その忙しさのまま稲刈りが始まった。 9月23日から27日まで4日間続けて稲刈りで、昨日も雨で刈取ができなかったが籾摺り […]
-
自分を言葉で表現する
今日は2件のイベントが入っていた。 一つは田植え体験をしたグループで、田んぼの草刈をして昼ごはんとして流しそうめんをした。 二つ目はその後に、天神のビルの屋上でペットボトルで稲を栽培するというグループの本場を見学するとい […]
-
大豆 播種
大豆の栽培は今年で5年目。しかし、今年も大豆は試験的な栽培にとどまっている。 理由、問題点はいくつもある。 まず大きな問題としてその採算。 1反あたり良品が100㎏と仮定して、1㎏あたり1000円だとしたら10万円プラス […]
-
無農薬・無肥料のお米で酒を造る
もう何年も前から酒米を育てて酒を造ってみたかった。 私はアルコール分解酵素をほとんど持ち合わせていないので、ビールでも50ml飲めば眠くなってしまうくらい。 それでも日本酒の味くらいはわかるもので、アルコールを添加してあ […]
-
9回目の田植えから早3週間
最近はSNSの台頭と、子供との時間を大切にしたいということからブログの更新が滞っていた。 しかし、初めて私を知った方がウェブサイトやブログを読んでくれて、農業のことや考え方のことなどのアイデンティティーについて知ってくれ […]
-
排水路の補修
もうブログを更新しなくなってある程度時間が経つがたまに「ブログみてます!」という嬉しい声を聞くとやっぱり記録してきてよかったと思える。 3月下旬から田 […]
-
イメージ
武井壮が陸上5種競技の元日本1位であることは知っていた。 彼は5種それぞれの種目においての練習はあまりせず、意識して練習していたのは「体を自分の思うように動かすこと」だったそうだ。 自分の体を自分の思うように動かすことが […]